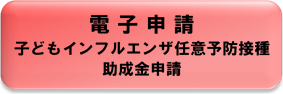子どもを対象としたインフルエンザ予防接種
令和7年10月1日から子どもを対象としたインフルエンザ予防接種の接種費用の一部助成を開始します。
令和7年10月1日より前に自費で接種した場合の償還払いの制度などはございませんのでご注意ください。
インフルエンザワクチンの納入時期は医療機関によって異なります。予防接種を希望する方は、事前に医療機関にワクチンの在庫状況等を確認することをお勧めいたします。
また、医療機関によっては予約が必要な場合があります。
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こります。症状の特徴は、普通のかぜに比べて高熱・筋肉痛・関節痛など全身症状が強いことです。気管支炎や肺炎などを合併して重症化することが多いのもインフルエンザの特徴です。
インフルエンザは、通常、初冬から春先にかけて流行します。インフルエンザにかかった人が咳やくしゃみなどをすることにより、口から発生する小さな水滴(飛沫)を、他の人が吸い込むことによって感染します。
インフルエンザの流行が始まると、短期間に小児から高齢者まで膨大な数の人を巻き込むという点が、普通のかぜとは異なります。小児では中耳炎の合併、熱性けいれんや気管支喘息の誘発、まれに急性脳炎などの重症合併症があらわれることがあります。
助成対象者
接種日現在、生後6月から高校3年生相当年齢の区民
使用ワクチン
インフルエンザHAワクチン(注射)
経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(2歳未満のお子さんは使用できません。)
接種期間
令和7年10月1日から令和8年1月31日まで
(接種期間外の接種は助成対象外です)
助成回数
インフルエンザHAワクチン
【生後6か月から13歳未満の方】
接種期間内に2回まで(接種間隔は2週間から4週間。免疫効果を考慮すると4週間が望ましいとされています。)
- 1回目の接種が13歳未満、2回目の接種が13歳の場合(どちらも接種期間内)は、2回とも助成対象です。
- 13歳未満は「13歳の誕生日の前々日まで」になります。
【13歳から高校3年生相当年齢までの方】
接種期間内に1回まで
経鼻弱毒生インフルエンザワクチン
【2歳から高校3年生相当年齢までの方】
接種期間内に1回まで
実施場所
助成金額
【インフルエンザHAワクチン】
1回あたり2,000円を助成
【経鼻弱毒生インフルエンザワクチン】
2歳から13歳未満の方、4,000円
※13歳未満は「13歳の誕生日の前々日まで」になります。
13歳以上から高校3年生相当年齢の方、2,000円
注意事項
・医療機関に支払う接種費用が、接種1回あたり上記助成金額分減額されます。
差額が生じた場合は自己負担となりますので、医療機関の窓口でお支払ください。自己負担額は医療機関ごとに異なります。金額は医療機関に直接ご確認ください。
★自己負担額=医療機関の定める接種費用ー北区助成金額
・予防接種は病気の予防のためであり治療ではないため、健康保険は適用されません。
・生活保護等を受けている方は、自己負担が免除されます。対応可能な医療機関についてはページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
接種方法(助成方法)
- 区内協力医療機関へ必要に応じて接種の予約をしてください。インフルエンザワクチンの在庫状況や接種費用、予約の要否等は直接医療機関にお問い合わせください。
- 接種日当日、以下の物をお持ちください。
- 北区の住所が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、乳幼児医療証や子ども医療証など)
- 母子健康手帳
- 助成を受けるために必要な予診票は、実施医療機関に設置しています。接種前の質問事項(体調や接種歴など)に回答してください。接種可能と医師が判断し、保護者が接種に同意した場合(16歳以上は本人の同意)、接種を受けることができます。
- 料金支払い時に、各医療機関が定める接種費用から助成金額が差し引かれます。
保護者の同伴
区の実施する予防接種は、原則保護者の同伴が必要ですが、保護者が特段の理由で同伴できない場合、保護者からの「委任状」により、保護者以外の人の同伴が認められています。同伴できる人は、普段からお子さんの健康状態をよく知っている人に限ります。
区内協力医療機関以外で接種する場合(国内で受けた接種のみ対象です)
対象の方で、やむを得ず区内協力医療機関以外で全額自己負担で接種を受けた場合につきましては、下部の電子申請リンクからご申請ください。
なお、この方法による助成の場合、健康被害が発生した場合の救済は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度のみ対象となりますのでご了承ください。
※申請期限は、接種した年度の末日です。
接種料金が助成金額を下回る場合は、接種料金分のお支払いとなります。
接種の際は、母子健康手帳を持参し、医療機関に接種記録の記入を依頼してください。
また、領収書を必ず受け取ってください。
申請に必要な書類
- インフルエンザ予防接種を受けた際の支払額が確認できる書類
- インフルエンザ予防接種の記録が確認できる以下の書類のいずれか1点の写し
- 接種につき記録された母子健康手帳(表紙と接種記録のページ)
- 接種に係る予防接種済証(被接種者氏名の記載があるもの)
- 接種済の記載がある予診票(被接種者氏名の記載があるもの)
- その他、接種日と接種したことがわかる書類(被接種者氏名もわかるもの)
- 申請者(保護者)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 助成金を入金する口座の情報が確認できる書類の写し(預金通帳の1ページ目、キャッシュカードなど)
電子申請は次のリンクからお進みください。(北区外で全額自己負担で接種した方用)
電子申請による申請が困難な方は、下記連絡先までご連絡ください。
〒114-0001
東京都北区東十条2-7-3
北区保健所保健予防課保健予防係
電話 03-3919-3104
ワクチンの効果と副反応について
インフルエンザ予防接種により、インフルエンザを予防したり、症状を軽くしたりすることが期待されます。また、インフルエンザによる合併症や死亡を予防することが期待されます。一方、副反応は一般的に軽微です。
HAワクチンの副反応として、予防接種の注射の跡が赤みを帯びたり、腫れたり、痛んだりすることがありますが、通常2~3日のうちに治ります。また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられることもありますが、通常2~3日のうちに治ります。
また、まれにアレルギー反応(発疹、湿疹、紅斑など)がみられることがあります。強い卵アレルギーなどのある方は、強いアレルギー反応を生じる可能性がありますので、接種前に必ず医師に申し出てください。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがあらわれることがあります。
経鼻生ワクチンの副反応として、鼻閉・鼻漏、咳、口腔咽頭痛、頭痛などがみられることがあります。また、重い副反応としてショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管性浮腫など)や、海外ではベル麻痺を含む脳神経障害、脳炎、けいれん(熱けいれんを含む)、血管炎(発熱、頭痛、倦怠感、紫斑、紅斑など)などが報告されています。また、2歳未満のお子さんが接種した際、入院及び喘鳴のリスクが増大したとされているため2歳未満のお子さんは使用できません。
このように予防接種の後には副反応が起こることがありますが、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なって現れることもあります。
予防接種を受けるときの注意
予防接種は体調の良い時に受けることが基本です。保護者の方は日ごろからお子さんの健康状態(体質、体調など)によく気を配り、何か心配なことがあれば、事前にかかりつけの医師に相談してください。
安全に予防接種を受けられるよう、保護者の方は、以下のことに注意してください。
- 当日はお子さんの状態をよく観察し、体調が悪いと感じたら、かかりつけの医師に相談の上、接種するかどうか判断しましょう。
- 予診票は、接種する医師が安全に予防接種を行うための情報です。記入もれのないよう注意しましょう。(体温は医療機関ではかります。)
- 母子健康手帳を忘れずに持っていきましょう。
- お子さんの日頃の健康状態をよく知っている保護者の方が連れて行きましょう。
予防接種を受けることができない方
- 明らかに発熱(通常37.5℃以上をいいます)がある場合
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
- 受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
- (経鼻のみ)明らかに免疫機能に異常がある疾患をお持ちの方、免疫抑制をきたす治療を受けている方
- (経鼻のみ)経口または注射の副腎皮質ホルモン剤を使用している方
- (経鼻のみ)妊娠していることが明らかな方
- その他、医師が不適当な状態と判断した場合
なお、現在、妊娠している方の場合は、接種することに注意が必要な方ですので、かかりつけ医とよくご相談ください。
他の予防接種との関係
他の予防接種との同時接種や接種間隔については、医師とご相談ください。
予防接種を受けた後の一般的注意事項
- 急な副反応が起こることがあるため、接種を受けた後30分間は接種した医師とすぐ連絡を取れるようにしておきましょう。
- 接種後は接種部位を清潔に保ち、接種した当日は激しい運動を避けてください。入浴は差し支えありませんが、注射ワクチンの場合は、注射部位をこすらないでください。
- 接種後4週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 接種後は自らの健康管理に注意し、もし、高熱や体調の変化、その他局所の異常反応に気づいた場合は、接種を受けた医療機関またはかかりつけ医へご相談ください。
予防接種による健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。インフルエンザ予防接種は任意接種であるため、万一、被接種者に健康被害が生じた場合は、予防接種法による健康被害救済制度の対象にはなりませんが、東京都北区予防接種事故災害補償要綱に基づく補償および医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象になることがあります。
お問い合わせ
北区保健所 保健予防課 保健予防係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-3104
- お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。
- お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。